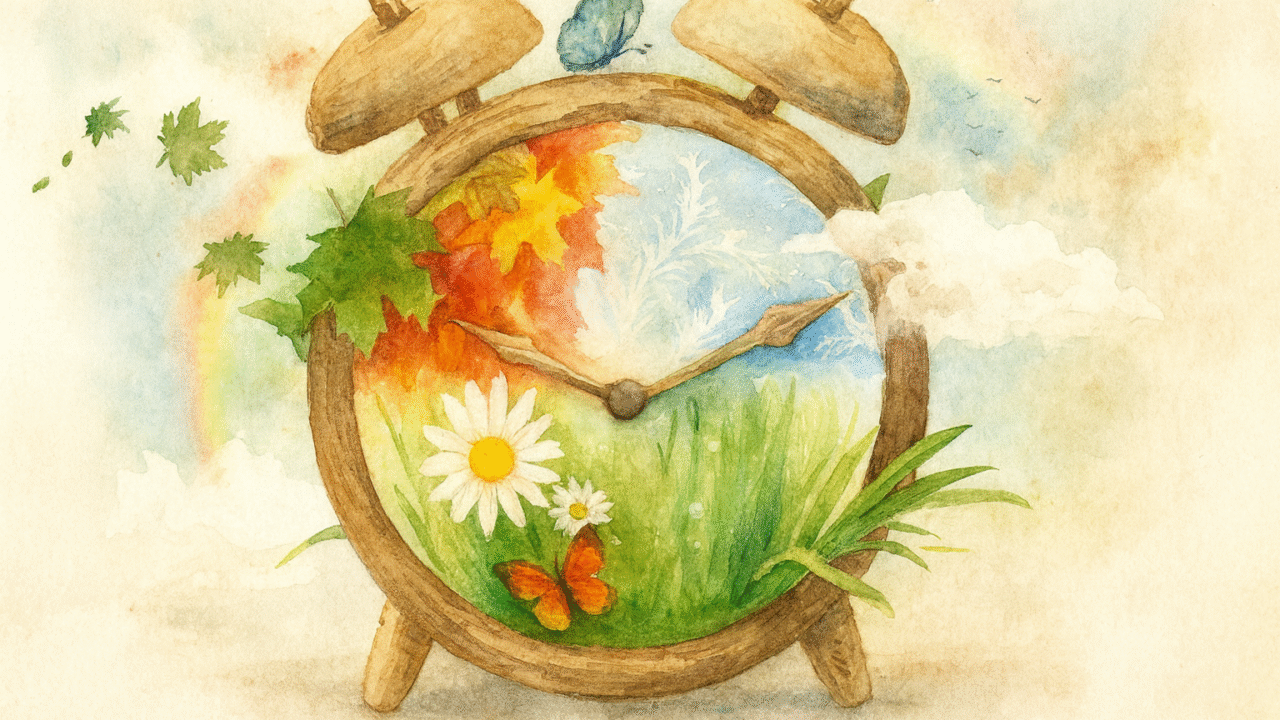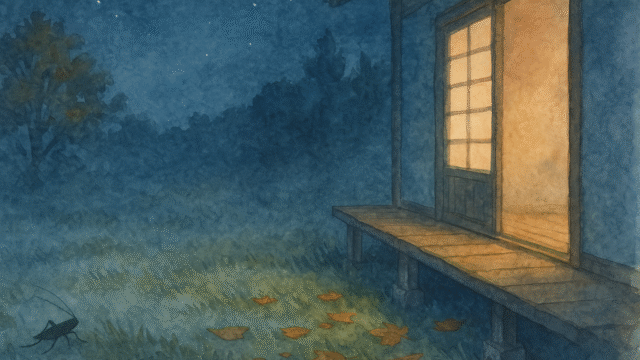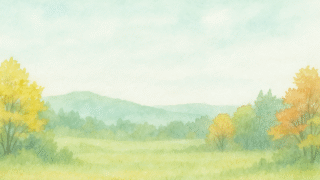カレンダーがなかった時代
私たちは今、手帳やスマホを開けば、日付や天気予報を簡単に確認できます。
けれど、カレンダーや時計のない時代、人々はどうやって季節の移ろいを知り、暮らしを整えていたのでしょうか。
その答えは、太陽や月、星、そして植物や動物たちの変化にありました。
自然こそが、最も正確で身近な「暦」だったのです。
日本に伝わった二十四節気
古代中国で生まれた二十四節気は、太陽の動きを基準に一年を24に区切ったもの。
春分・夏至・秋分・冬至はその代表です。
季節の移り変わりを知らせるだけでなく、田植えや収穫といった農作業の目安にもなりました。
日本には平安時代頃に伝わり、稲作を中心とした生活に深く根付きました。
暦としての実用性に加え、和歌や歳時記の題材としても人々の感性を育ててきたのです。
七十二候 ― 自然を映す細やかな暦
さらに一年を5日ごとに分け、72の小さな季節にしたものが七十二候です。
「雷乃収声(雷が鳴りをひそめる)」「蟄虫坏戸(虫が土に隠れる)」など、自然界の変化がそのまま名前になっています。
農作業の目安であると同時に、日々の心のあり方にも影響を与えていました。
「今日は雷が鳴らなくなったから季節が変わる」「虫が土に隠れる頃だから冷え込みに備えよう」といったように、小さな合図を頼りに生活していたのです。
世界の暦と人々の工夫
暦を生み出したのは日本だけではありません。
世界中で、人々は自然を観察し、それを生活の知恵に変えてきました。
- 古代ローマでは月の満ち欠けを基準とした暦が使われていましたが、季節とのずれが大きく、ユリウス暦(紀元前46年)やグレゴリオ暦(1582年)へと改良されました。私たちが今使っている西暦のカレンダーは、この流れを受け継いだものです。
- イスラム暦は現在も月の満ち欠けを基準にした太陰暦。ラマダーンの時期などは月の動きを観測して決められます。
- マヤ文明は、太陽や惑星の動きを基にした高度な暦を作り、祭礼や王朝の政治に利用しました。
- ヨーロッパのケルト文化では、火祭りや収穫祭が太陽の動きと結びついており、季節を祝う行事が人々の心を支えていました。
世界中の暦に共通しているのは、「暦がただの日付の管理ではなく、人々の心や文化を形づくるものだった」ということです。
暦がくれる心の整え方
現代は便利なカレンダーがある一方で、自然のリズムを忘れてしまいがちです。
けれど、二十四節気や七十二候を思い出すと、「自然とともに暮らす感覚」を取り戻せます。
雷が静まり、虫が眠り、水が涸れていく。
そんな言葉に耳を傾けるだけで、私たちの心も少し静まり、整っていくように感じませんか。
まとめ
二十四節気や七十二候は、昔の人にとって「自然が教えてくれる暦」でした。
世界でも同じように、人々は空や大地を見上げ、季節を知り、生活を築いてきました。
暦は便利なツールであるだけでなく、心と体を自然と調和させる知恵でもあるのです。
そしてこれから少しずつ、二十四節気や七十二候の紹介とあわせて、心身を整える方法や、季節に寄り添うハーブやアロマについてもお伝えしていきます。
森と心を結ぶタロット時間 | ハーブと香りで読み解く心のタロット講座 ~癒しから仕事へ~をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。