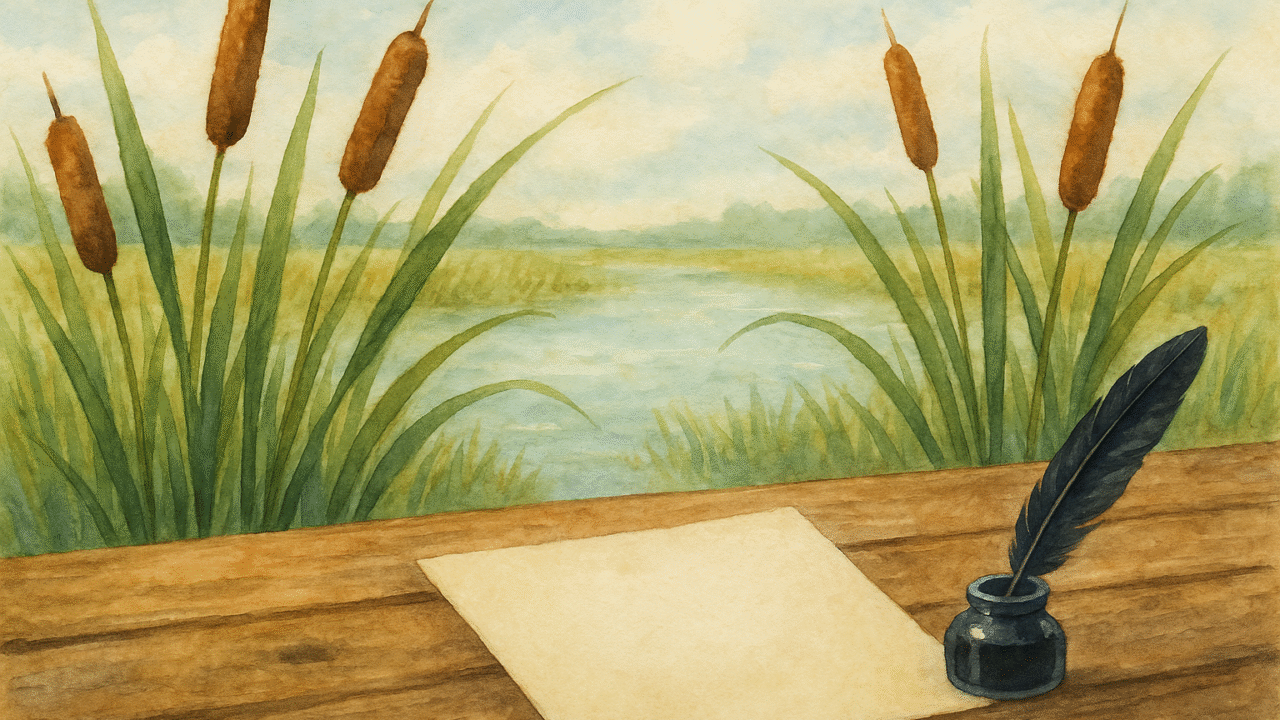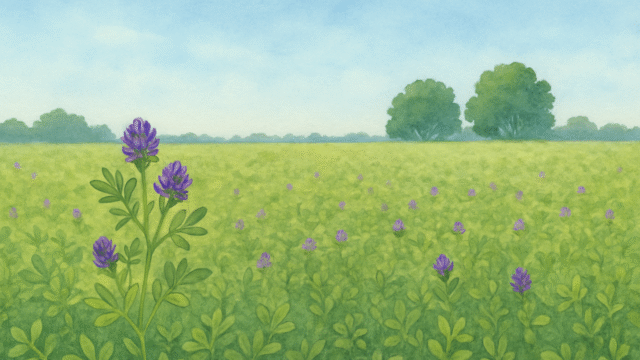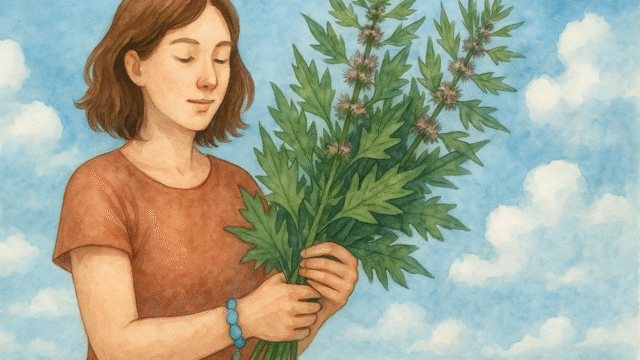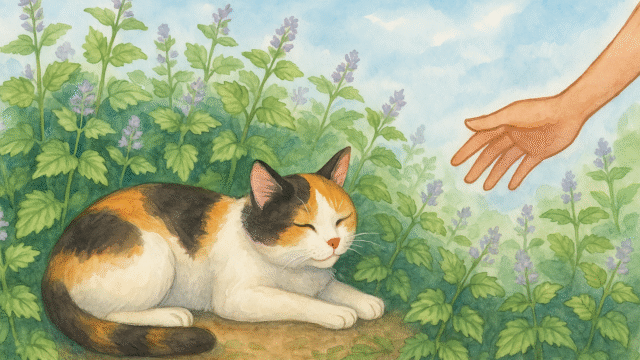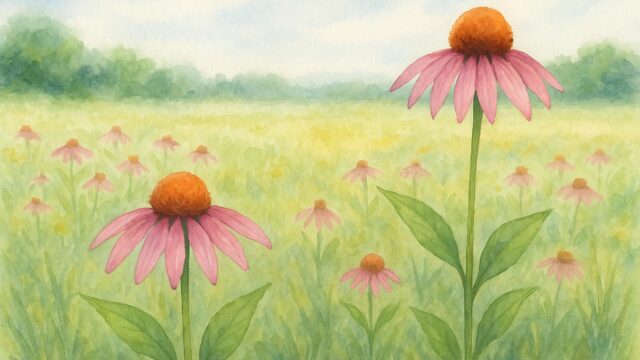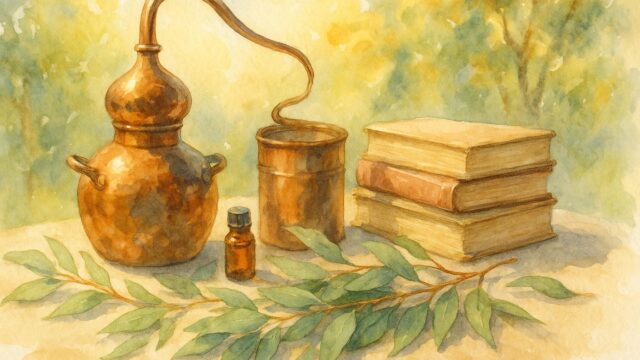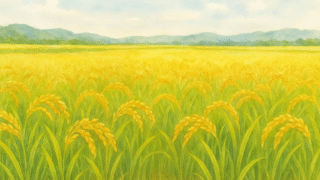布団と座布団の語源
私たちが毎日使う「布団」。
実は語源をたどると「蒲(ガマ)」に行きつきます。
ガマの穂の綿毛はふわふわで軽く、保温性も高いため、古くは敷物や寝具に詰め物として使われていました。
そこから「蒲団(ふとん)」という言葉が生まれ、今の布団につながっています。
また、禅僧が座禅をするときに用いたクッションも、もともとはガマを詰めた「座蒲(ざふ)」。
ここから「座蒲団(ざぶとん)」の言葉が定着しました。
蒲焼きとかまぼこの由来
食文化にもガマは登場します。
- ・蒲焼(うなぎのかばやき):昔はウナギを丸ごと串に刺して焼いていました。その姿がガマの穂に似ていたため「蒲焼」と呼ばれるようになったといわれます。
- ・かまぼこ:平安時代には魚のすり身を竹や棒に巻きつけて焼いた「蒲鉾」がありました。これもやはり形がガマの穂に似ていたから。今の板かまぼこは後の時代に広まった姿です。
こうして見ると、ガマは「寝具」から「料理」まで、日本人の暮らしに深く結びついてきたことがわかります。
🌿 ガマの効能と使い道
ガマは「野生のスーパーマーケット」とも呼ばれます。
- 食用:若芽は野菜に、花粉は粉食に、根茎は澱粉源に。
- 薬用:花粉(蒲黄)は止血薬として、根は利尿・消炎に。
- 生活利用:葉は屋根材や籠、穂の綿毛は寝具や火口に。
一見ただの湿地の植物が、人間の暮らしを何重にも支えてきたのです。
Six of Air × CATTAILのメッセージ
Herbcrafter’s Tarot の「Six of Air」に描かれたガマもまた、「濁った場所から明晰さをもたらし、人と人をつなぐ植物」として示されています。
布団や座布団、蒲焼や蒲鉾のように、ガマは日常の中で形を変えながら私たちを支えてきました。
それはまるで、思い込みを手放し、新しい視点を取り入れることで暮らしが整っていく姿に重なります。
このカードが伝えるのは――
「あなたの思い込みを問い直し、祈りや意図を言葉にして、仲間と分かち合うことで、人生はより明るくなる」 ということ。
ガマの種が風に乗って広がるように、あなたの思いや願いもきっと、必要な場所へ届いていくはずです。
まとめ
ガマは野草として見過ごされがちな植物ですが、実は「野生のスーパーマーケット」と呼ばれるほど万能。
布団や料理にその名を残し、今も私たちの言葉や文化に息づいています。
Herbcrafter’s Tarot《Six of Air × Cattail》が伝えるように、
「思い込みを問い直し、仲間と意図を分かち合い、風にのせて願いを広げていく」――
そんな気づきを、ガマはそっと教えてくれているのかもしれません。
森と心を結ぶタロット時間 | ハーブと香りで読み解く心のタロット講座 ~癒しから仕事へ~をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。