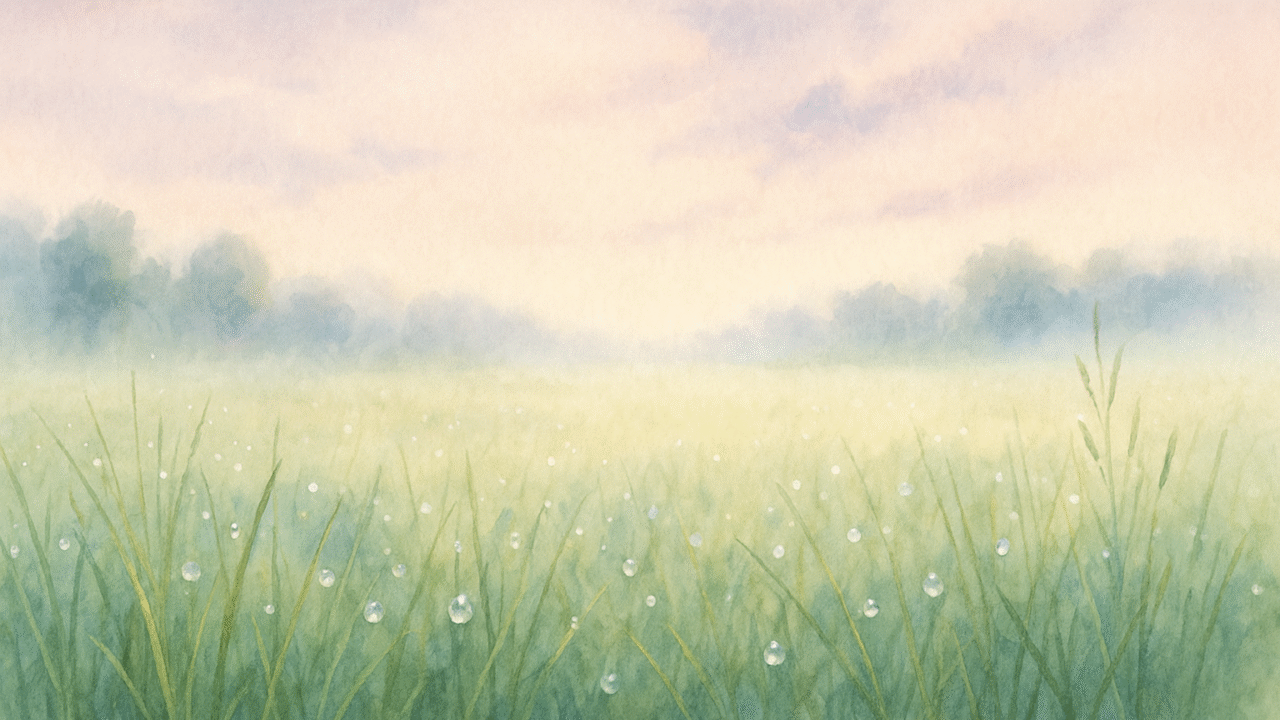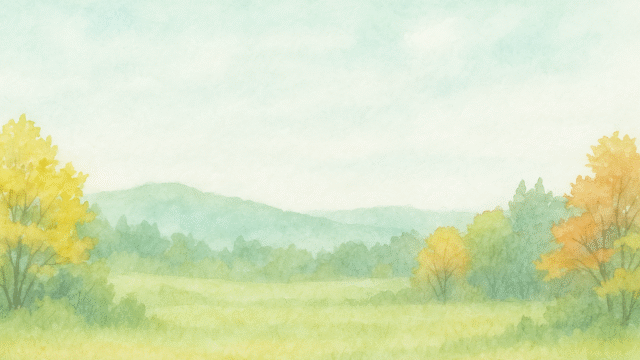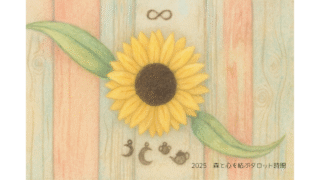【二十四節気】寒露とは 2025年10月8日~10月22日
寒露(かんろ)は、二十四節気の第17番。
毎年10月8日ごろに訪れ、白露よりさらに冷気が増し、草木に宿る露が冷たく感じられるようになる頃を指します。
暦便覧には、「陰寒の気に合つて露結び凝らんとすれば也」とあり、露が結び、やがて凍り始める寸前の寒さを想像させる言葉です。
また、寒露の期間はこの日から「霜降(そうこう)」の前日まで。
秋がさらに深まり、朝晩の冷え込みが本格化していく時期でもあります。
この頃、空気は澄み渡り、秋晴れの日が多くなります。
野の草木には冷たい露が降り、やがて霜に変わる前の“透明な静けさ”が漂います。
鴻雁(こうがん/雁)が南へ渡り始め、秋の虫の声がより強く響くようになり、木々は少しずつ紅葉をまとい始めます。
実りと変化が重なり合う、秋の終盤の入り口です。
昔の人にとって、寒露は「秋の終盤を見定める節目」でした。
露の冷たさという自然のサインを頼りに、稲刈りや野菜の収穫、貯蔵の準備など、次の季節への備えを整えていたのです。
二十四節気や七十二候は、自然の微妙な変化を言葉として暮らしに取り入れた“自然の暦”。
寒露もまた、冬に向けて心と体を整えるための目印のひとつです。
季節に重なる伝統色「霞色(かすみいろ)」
朝晩の冷え込みがはっきりと感じられる頃。空気が澄み、草の葉には冷たい露が降り、秋の深まりを肌で感じる季節です。
この時期に重ねたい伝統色は「霞色(かすみいろ)」。
灰がかった淡い青紫で、朝霧に包まれた山の輪郭や、夜明け前の空気のような静けさを感じさせる色です。
強さではなく、やわらかな冷たさ。
寒露という言葉にある“透明な静寂”を、美しく映し出してくれます。
寒露にともなう七十二候
寒露の時期には、次のような七十二候が巡ります。
- 鴻雁来(こうがんきたる):雁が北から渡ってくる
- 菊花開(きくのはなひらく):菊の花が咲き始める
- 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり):虫の声が家の近くで響く
昼は高く澄んだ空、夜は虫の音。季節の移ろいが静けさの中に滲み、自然が冬への支度を始める時期です。
体を潤し、気持ちよく過ごすために
乾燥と冷えが少しずつ進むこの時期、漢方の考えでは「肺」を整えることが大切とされています。
肺は“気”の巡りと深く関わる臓器。
潤いが不足すると、喉や肌の乾き、咳、気分の落ち込みにもつながります。
おすすめの過ごし方:
- ・朝の白湯やハーブティーで、喉と体を内側から温める
- ・梨、蓮根、白きくらげなど、潤いを補う食材を取り入れる
- ・ゆっくり深呼吸しながらのストレッチで「気」の流れを整える
- ・お風呂の後にオイルやクリームで肌を保湿する
体を潤すことは、心をやわらげることにもつながります。乾燥を防ぎながら、温かさを意識して過ごしましょう。
ママへのセルフケアのヒント
秋の夜は長く、ふとした瞬間に心が静まりすぎて、少しさみしさを感じることがあります。
そんなときは無理に気分を上げようとせず、“静けさを味わう時間”にしてみてください。
- ・子どもが寝たあと、灯りを落として温かいカモミールティーを飲む
- ・アロマランプでオレンジやフランキンセンスを焚き、深く呼吸する
- ・夜空を見上げて、月や星を静かに眺める
季節の静けさを受け入れると、心は自然にゆるみ、次の季節を迎える準備が整っていきます。
🍂 まとめ
寒露は、露が冷たく感じられ、自然が冬支度を始める季節。
霞色が映すのは、冷たい空気とやさしい光が交わる、わずかな時間の美しさです。
心も体も「ゆっくり整える」ことを意識して、季節の静けさを味方にしましょう。
これからも、二十四節気や七十二候とともに、心と体を整える暮らし方をお届けしていきます。
森と心を結ぶタロット時間 | ハーブと香りで読み解く心のタロット講座 ~癒しから仕事へ~をもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。